苦情が来る前に確認!悪臭防止法における届け出と改善の流れ
悪臭防止法の基本から対象物質・測定方法・事例までを専門家が解説。におい対策の第一歩として、必要な知識と対応のヒントが得られます。
悪臭防止法とは?
においは人の記憶や感情と深く結びついていますが、不快なにおいは健康や生活環境に悪影響を及ぼすことがあります。悪臭防止法は、そうした「においの害」から人々を守るために作られた法律です。この法律は工場や飲食店などの事業者だけでなく、近隣住民や働く人々、さらには通行人までも対象に含んでいます。悪臭による苦情は、全国で年間数千件にのぼり、住宅地や学校周辺ではとくに敏感な問題です。そこで、においを「主観的な不快感」だけでなく、客観的に測定・規制する枠組みとして、この法律が機能しています。

日常生活や事業活動でなぜ悪臭が問題になるのか
たとえば、焼き肉店やクリーニング工場の近くに住む人が「においがきつくて窓が開けられない」と感じた場合、それは生活の質に直結する問題です。悪臭は気分の悪化や頭痛などの体調不良を引き起こすこともあり、健康被害にもつながるおそれがあります。さらに、観光地や住宅地では「においの印象」が町全体のイメージや不動産価値にまで影響を与えることがあります。事業者にとっても、近隣からの苦情が繰り返されれば営業停止や評判の低下を招く可能性があるため、においの管理は重要な経営課題です。
法の目的と基本的な考え方
悪臭防止法の目的は、「においによる被害を未然に防ぎ、住民の快適な生活環境を保つこと」です。法律では、特定のにおい物質やにおいの強さ(臭気指数)を基準にし、施設の種類や場所によって異なる規制値が定められています。また、苦情が多発した場合、自治体が規制地域を指定し、対象事業者に改善を求める仕組みもあります。つまり、においという「見えない問題」に対して、数値とルールを使って対応するのがこの法律の特徴です。
においの感じ方には個人差がありますが、それでも共通の基準で「どこからが問題か」を判断できるようにするために、この法律が存在しています。悪臭を減らすことは、住民の安心感を生み、事業者にとっても信頼性のある運営につながります。
悪臭に関する研究および悪臭防止技術の開発の進展、悪臭の防止に対する国民の世論の高まりを背景に1971年に悪臭防止法が制定され、特定悪臭物質の濃度による規制が始まった。
▶︎出典:悪臭防止法|フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
対象となるにおいと規制のしくみ
悪臭防止法では、においの発生源を明確にし、それに対して具体的な基準を設けて規制するしくみが整えられています。対象となるにおいは、単なる「不快」といった感覚だけでなく、科学的に成分や強さが測定できるものに限定されています。これにより、誰が判断しても同じ結果が得られるようにし、トラブルの解決につなげています。

特定悪臭物質22種とは?
悪臭防止法では、においの原因となる「特定悪臭物質」が22種類定められています。これらは、生活環境に影響を与える恐れがあると国が判断した化学物質で、以下のようなものが含まれます。
| 物質名 | 主なにおいの特徴 | よくある発生源 |
|---|---|---|
| アンモニア | 刺激のある尿のようなにおい | 肥料、動物排せつ物 |
| 硫化水素 | 腐った卵のようなにおい | 下水、温泉施設 |
| メチルメルカプタン | 腐ったキャベツ臭 | 食品工場、ごみ処理施設 |
| アセトアルデヒド | 刺激臭、接着剤のにおい | 印刷工場、建材 |
| トリメチルアミン | 魚が腐ったようなにおい | 魚介類の加工場 |
これらの物質は、濃度によってにおいの強さが決まり、一定の基準値を超えると法的な対応が求められます。
臭いの種類と感じ方の違い
同じ物質でも、においの感じ方には個人差があります。たとえば、硫化水素は「腐った卵のにおい」と表現されますが、濃度が低いと気づかれにくく、逆に高濃度では嗅覚がまひしてしまいます。
| 系統 | 代表物質 | においの表現例 |
|---|---|---|
| 窒素系 | アンモニア、トリメチルアミン | 尿・腐敗した魚 |
| 硫黄系 | 硫化水素、二硫化メチル | 腐った卵・ガス |
| 酸系 | 酢酸、酪酸、プロピオン酸 | 汗、すえたにおい |
| 有機溶剤系 | トルエン、スチレン | ペンキ、接着剤のにおい |
とくに、トリメチルアミンやメチルメルカプタンは極めて低濃度でも強く感じられるため、検出しやすく、苦情につながりやすいにおい物質です。
臭気指数と物質濃度のちがい
においを数値で表すには、2つの方法があります。「物質濃度」は、空気中に含まれるにおい成分の量を直接測定する方法です。たとえば、「1立方メートルあたりアンモニアが0.6ppm(百万分率)含まれる」といった数値で示されます。
一方、「臭気指数」は、においの強さを人の感覚で評価したあと、それを数値化したものです。においを薄めていき、「においを感じなくなるまで何倍に希釈したか」に基づいて算出されます。人の感じ方をもとにした数値なので、生活環境における実感と近い評価ができます。
においの規制方式(物質濃度規制と臭気指数規制)
悪臭防止法には、「物質濃度規制」と「臭気指数規制」という2つの方式があります。
- 物質濃度規制:特定悪臭物質が対象。排出ガス中の成分を機械で測定し、国が定めた濃度基準を超えないように規制されます。
- 臭気指数規制:人の嗅覚による評価が中心。悪臭の種類に関係なく「どのくらいにおうか」が問題になる場合に適用されます。
どちらの方式を採用するかは自治体ごとに異なり、事業者は地域の規制方式に合わせて対策をとる必要があります。
におい対策を成功させるためには、自社の排出するにおいが「どの物質に該当するか」「どの方式で規制されるか」を正しく理解することが出発点となります。
規制基準と適用エリア
悪臭防止法の規制は、日本全国どこでも一律に適用されるわけではありません。においの感じ方や周辺環境の状況は地域によって異なるため、自治体ごとに独自の基準やルールが設けられています。こうした地域ごとの規制体制を理解することは、事業者だけでなく一般市民にとってもトラブルを避ける重要なポイントです。

規制地域の指定方法と施行令との関係
悪臭防止法では、都道府県や市区町村が「規制地域」を指定することができます。この指定は、地域で悪臭による苦情が多発していたり、将来的に問題が起きそうな場合に行われます。たとえば、住宅地や学校の周辺、観光地の近くなど、においへの配慮が求められるエリアが優先される傾向があります。
このときに根拠となるのが「施行令」です。施行令には、どのようなにおいが対象か、どのように規制地域を決めるかといった具体的なルールが定められています。自治体はこの施行令をもとに、地域の特性や住民の声を反映しながら、実際の運用方法を決定しています。
敷地境界や排出口など場所別の基準値(1号〜3号規制)
悪臭防止法では、においをどこで測るかによって規制の厳しさが異なります。これを「1号規制」「2号規制」「3号規制」と呼び、次のように分類されます。
- 1号規制(敷地境界):事業者の敷地の外側でにおいを測定。他人の土地ににおいが漏れないようにする目的です。
- 2号規制(排出口):煙突や換気扇など、においが外に出る場所で測定。装置からの排出基準が定められています
- 3号規制(排水):においを含む水の排出(例:排水溝)に対する基準。あまり一般的ではありませんが、特定施設では重要です。
これらの規制は、発生源の種類や周辺の環境によって適用されるかどうかが異なります。たとえば、住宅地に隣接する工場では、1号規制が重視されることが多くなります。
自治体による違いと検索のコツ
においに対する規制は、地域によって細かく異なるため、自分の住んでいる場所や事業所がある自治体のルールを確認する必要があります。たとえば、東京都では「臭気指数規制」が導入されていますが、他の県では「物質濃度規制」が主流というケースもあります。
確認する際は、「〇〇市 悪臭防止法 規制地域」「〇〇県 悪臭防止法 基準値」といったキーワードで検索すると、自治体の公式サイトや環境課のページが見つかりやすくなります。においに関するトラブルは、事前の情報収集と適切な対応で回避できるケースが多くあります。まずは、自分の地域の「においのルール」を知ることが、におい対策の第一歩です。
施行規則と届出の流れ
悪臭防止法は、においの発生を抑えるための枠組みですが、実際の運用は「施行令」や「施行規則」によって細かく決められています。とくに事業者にとっては、どんなときに届出が必要なのか、行政からの指導はどう進むのかといった流れを理解しておくことが大切です。手続きの遅れや不備があると、トラブルや営業への支障につながるおそれがあります。

施行令・施行規則の違いと役割
悪臭防止法には、法律そのものに加えて「施行令(せこうれい)」と「施行規則(せこうきそく)」という2つの細かいルールがあります。
- 施行令は、法律の大枠をもとに、においの種類や規制方式、対象地域の指定方法などを定めています。国が決めるもので、すべての自治体で共通です。
- 施行規則は、さらに細かい実務的なルールで、届出の方法や書類の形式、測定結果の報告様式などが含まれます。実際ににおい対策を進めるうえで、事業者が直接関わるのはこちらです。
つまり、施行令は「何を守るか」、施行規則は「どうやって守るか」を示していると考えるとわかりやすいでしょう。
対象施設と届出が必要なケース
すべての施設が悪臭防止法の届出対象になるわけではありません。届出が必要となるのは、規制地域にある施設で、特定悪臭物質を扱ったり、においが強く出る作業を行ったりしている場合です。たとえば、以下のような施設が対象となることがあります。
- 食品加工場(乾燥、発酵、加熱などの工程がある場合)
- 畜産施設(鶏舎・豚舎など)
- 廃棄物処理施設
- 印刷や化学製品の製造工場
届出は、施設の新設・増設・変更の際に必要です。提出先は、施設の所在地を管轄する自治体の環境担当課などで、事前に相談するのが望ましいです。
届出から測定・改善命令までの行政フロー
届出を行うと、自治体はその内容をもとににおいの発生状況をチェックし、必要に応じて立ち入り調査や臭気測定を行います。測定の結果、基準値を超えていた場合には、以下のような手順で行政指導が進みます。
- 改善の指導・助言:まずは任意の対応を促されます。
- 勧告・命令:改善が不十分な場合、正式な行政命令が出されます。
- 公表・罰則:命令に従わないと、事業者名の公表や過料(罰金)などが科される場合があります。
このように、行政とのやりとりは段階を踏んで進行します。においの問題は一度発生すると近隣住民との信頼関係にも影響を与えるため、届出の義務がある場合は必ず期日内に提出し、誠実な対応を心がけることが重要です。
個人や小規模事業者にも関係あるの?
悪臭防止法と聞くと「大きな工場や施設だけが対象」と思われがちですが、実は個人の家庭や小規模な店舗でも、状況によっては規制や苦情の対象になることがあります。とくに人口密度が高い住宅街や商業エリアでは、においへの感受性が高く、わずかな変化でもトラブルにつながる可能性があります。自分では「それほどにおわない」と感じていても、他人にとっては強烈に不快な場合もあるのです。

一般家庭でも注意すべきにおいの種類
家庭で発生するにおいには、生活に必要な行為にともなうものも多くありますが、次のようなにおいはとくに注意が必要です。
- ごみのにおい:生ゴミやペットシートの処理が遅れると、腐敗臭が発生しやすくなります。
- ペット臭:室内飼育や多頭飼育の場合、獣臭や糞尿のにおいが近隣に漏れることがあります。
- ベランダの喫煙:たばこのにおいは壁や布に染みつき、風で広がるため苦情が多いです。
- 料理のにおい:焼き魚や揚げ物など、強いにおいが長時間続くとトラブルの原因になります。
いずれも、換気扇の位置や時間帯に配慮するだけで、においの広がりをかなり抑えることができます。
飲食店・美容室・農業施設の注意点
小規模店舗や自営業でも、においによって近隣からのクレームが発生するケースは少なくありません。たとえば以下のような業種が、におい対策を求められることがあります。
- 飲食店:焼肉、焼き鳥、ラーメン店などは調理中の煙や脂のにおいが強く、排気ダクトの管理が不可欠です。
- 美容室:パーマ剤やカラー剤の化学臭が、通行人や隣接住民にとって不快に感じられることがあります。
- 農業施設:堆肥、家畜、飼料などのにおいが強い場合、風向きや気温によって広範囲に影響を与えることもあります。
これらの業種では、脱臭フィルターや排気の方向調整、においの強い時間帯の短縮など、簡単な工夫から始めることが可能です。
苦情が入った場合の対応とリスク
においに関する苦情が自治体や警察に寄せられると、行政からの調査や指導が入ることがあります。とくに悪臭防止法の「規制地域」に指定されている場所では、苦情が繰り返されると事業所名が公表されたり、改善命令が出されたりするリスクもあります。
苦情が入った際に取るべき対応としては、以下のような点が挙げられます。
- まずは事実確認を行い、どのにおいが問題かを把握する
- 近隣への聞き取りや第三者の測定を依頼する
- 謝罪や改善策を丁寧に説明し、信頼回復を図る
においの問題は「感じ方のちがい」によって深刻化しやすく、対応が遅れると関係悪化につながります。小さな兆候でも軽視せず、丁寧に向き合うことが、長く地域で活動していくための大切な姿勢です。
測定方法と専門資格
においは目に見えず数値でも捉えにくいため、「どのくらいにおうか」「どこからにおっているのか」を正しく判断するのは簡単ではありません。悪臭防止法では、専門的な測定方法や機材を使って、においを客観的に評価する仕組みが整えられています。これにより、苦情や規制の対応を感情や主観だけに頼らず、科学的に進めることが可能になります。

においの測定方法と機材の種類
においを測る方法には、大きく分けて「感覚的測定」と「機器分析測定」の2種類があります。
- 感覚的測定(三点比較式臭袋法):人の嗅覚を使って、においを薄めながらその強さ(臭気指数)を数値化する方法です。においを嗅ぎ分けるための専門訓練を受けた複数の人が判定に参加します。
- 機器分析測定:ガスクロマトグラフやにおいセンサーなどを用いて、空気中の特定悪臭物質の濃度を化学的に測定します。においの種類と量を数値で確認できるのが特徴です。
使用する機材には、以下のようなものがあります。
| 測定機材 | 主な用途 |
|---|---|
| 臭気測定用バッグ | 空気を採取して持ち帰るための器具 |
| ガスクロマトグラフ | 成分ごとの濃度を分析する高精度機器 |
| ポータブル臭気センサー | 現場で簡易的に臭気を測る携帯機器 |
測定の正確性を確保するためには、環境や時間帯にも注意しながら実施することが重要です。
臭気判定士とは?資格と役割
においの評価には専門的な知識と感覚が求められます。そこで活躍するのが「臭気判定士(しゅうきはんていし)」です。これは環境省が認定する国家資格で、嗅覚のトレーニングと法令・化学の知識をもった専門家が試験を経て取得できます。
臭気判定士の主な役割は以下の通りです。
- 感覚的測定におけるパネリスト(判定者)を務める
- 測定計画の立案や結果の解析を行う
- 行政や事業者へのアドバイスや改善提案を行う
においは人によって感じ方が異なるため、訓練された専門家による評価が非常に重要です。臭気判定士はその信頼性を担保する存在といえます。
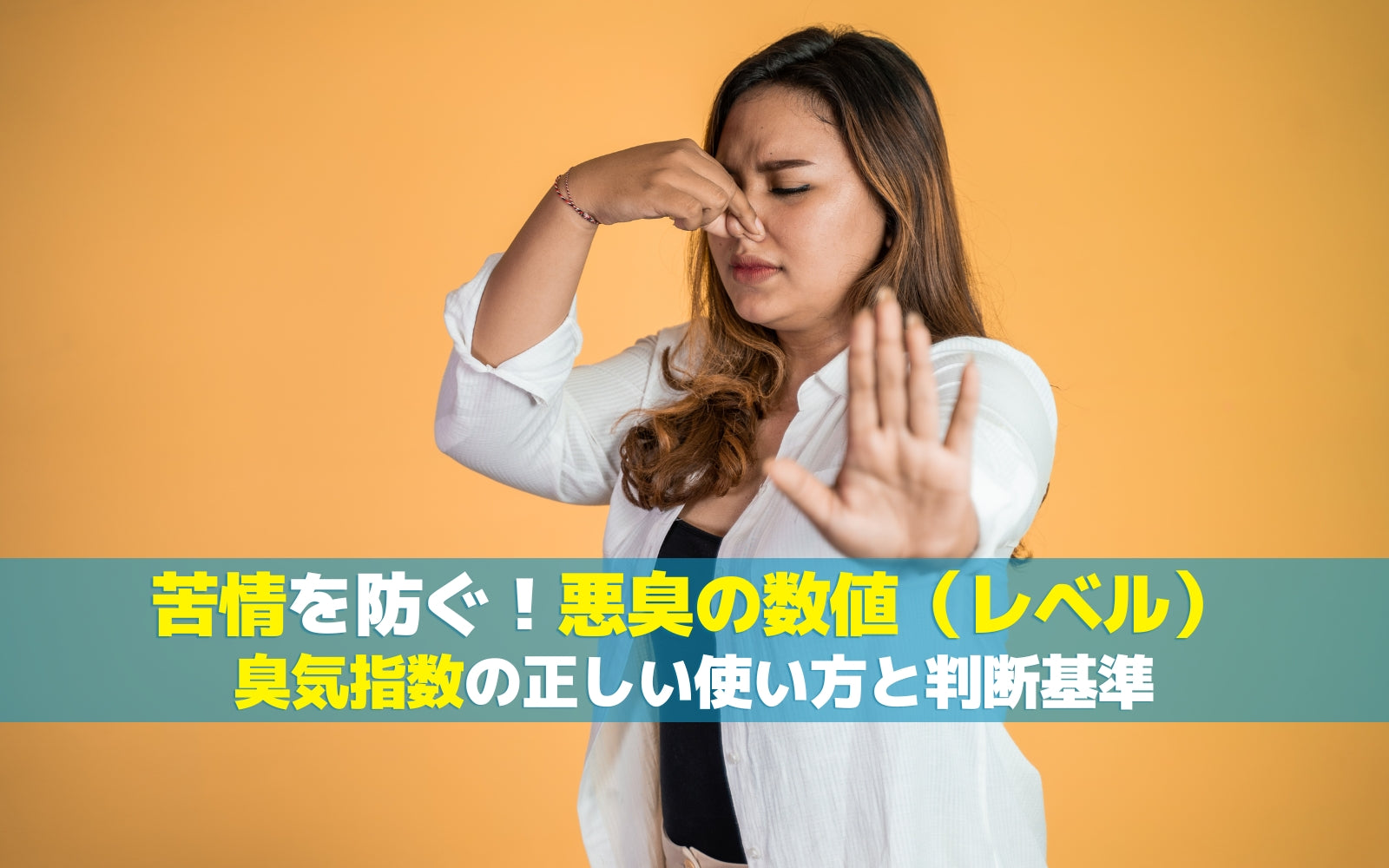
悪臭の数値(レベル)臭気指数は、においを数値で客観的に評価するために不可欠な指標です。本記事では、臭気指数の定義、測定方法、規制基準や対応策を解説します。
▶︎ 記事をチェック自主測定と第三者機関の使い分け
事業者がにおい対策を進めるうえで、「自主測定」と「第三者機関による測定」をどう使い分けるかは大きなポイントです。
- 自主測定:自社内でにおいの発生状況を把握する目的で行います。日常のモニタリングや改善前後の効果確認に適しています。
- 第三者測定:信頼性が求められる場面(例:苦情対応・行政報告)では、専門機関や臭気判定士に依頼するのが一般的です。
とくに苦情が入ったときや行政とのやり取りが必要になった場合、客観的なデータとして第三者の測定結果は大きな説得力を持ちます。
においの問題を感情的な対立にせず、客観的な根拠をもって冷静に対応するためにも、測定の仕組みと専門家の活用は欠かせない手段です。
実例で見る悪臭トラブルと対策
においの問題は、規模や業種にかかわらずあらゆる場面で発生します。とくに悪臭は目に見えないため、当事者にとっては気づきにくく、対応が後手にまわってしまうことも少なくありません。この章では、実際に起きた悪臭トラブルの事例と、その対策方法や費用感、さらにトラブルを未然に防ぐための工夫を紹介します。

工場での改善事例とコストの目安
化学製品を扱う工場などでは、作業工程で発生するにおいが近隣に影響を及ぼし、「頭痛がする」「洗濯物が干せない」といった生活上の支障を訴えられるケースがあります。敷地境界での臭気指数が基準を超えていた場合には、排気設備の見直しや脱臭装置の導入などが求められることもあります。
対策として以下のような措置が挙げられます。
- 排気口に活性炭フィルターを導入
- 排気ダクトの高さを延長し、においの拡散を軽減
- 夜間の作業を制限し、においの発生時間を短縮
対策にはまとまった費用がかかることもありますが、においの苦情がなくなり、地域との関係が良好になるなど、結果的に事業継続の安心材料となることも多いです。
自治体対応の好事例・失敗事例
においに関する苦情は、住民と事業者の間だけでなく、自治体の対応によっても結果が大きく左右されます。ここでは、実際の自治体対応に関する事実に基づいた傾向を紹介します。
苦情受付から現地調査、指導までの一貫対応
多くの自治体では、悪臭に関する苦情が寄せられた場合、次のようなフローで対応しています。
- 苦情内容のヒアリング
- 現地での臭気確認および測定(必要に応じて)
- 関係事業者への助言・指導
- 改善状況の確認と再発防止策の支援
たとえば長野県では、環境保全に関する公害苦情への対応として、関係部局と連携しながら調査・指導・助言を実施していると明記されています(長野県公式サイトより)。また、他県でも環境部局や保健所が中心となり、迅速な現地確認を行う体制を整えている例が見られます。
苦情受付から現地調査、指導までの一貫対応
一方で、自治体内での担当部門の連携不足や判断の遅れにより、苦情の対応が後手にまわり、住民の不満が大きくなるケースも報告されています。とくに、情報共有が不十分な場合、住民・事業者・行政の三者間で信頼関係が損なわれ、問題が長期化する要因になります。こうした事態を防ぐために、自治体ごとの対応マニュアル整備や、臭気測定機材・技術の導入、専門家(臭気判定士など)との連携強化が求められています。
SNSや近隣トラブルへの影響と回避策
近年はSNSの普及により、悪臭トラブルが瞬時に拡散されるリスクがあります。たとえば、「○○工場の前、くさすぎて吐きそう」などの投稿が拡散されれば、企業イメージの失墜や風評被害にもつながりかねません。しかも、においの原因がはっきりしない場合でも、名指しで批判されることがあります。
このようなリスクを回避するためには
- 日頃からにおい対策の見える化(対策内容をHPで公開するなど)
- 近隣住民との定期的な対話の場の設置
- 苦情対応マニュアルの整備と社員教育
といった取り組みが有効です。
におい問題は放置すれば信頼の崩壊につながりますが、誠実に向き合えば、逆に地域との信頼を深めるチャンスにもなります。対応の早さと情報の透明性が、今後ますます重要になるでしょう。
悪臭対策を成功させるポイント
においの問題は、見えにくく測りにくいため、対応が後回しになりがちです。しかし、悪臭は近隣との信頼関係や企業の評価、さらには健康や生活の質にも深く関わる重要な課題です。ここでは、これまでの内容をもとに、悪臭対策を成功に導くためのポイントを整理してご紹介します。

成功のための5つの基本ポイント
①においの見える化
においは感覚的なものだからこそ、臭気指数や物質濃度で「数値化」することが重要です。測定データは、社内外への説明や改善の根拠として大きな力を持ちます。
②地域のルールを把握する
悪臭防止法の適用内容は自治体ごとに異なります。自社の所在地が「規制地域」に入っているか、どの規制方式が採用されているかを事前に確認しておきましょう。
③においが出る工程を特定する
発生源の特定が対策の第一歩です。製造工程や排気口のチェック、時間帯ごとのモニタリングなどを通じて、においのピークを把握します。
④無理のない改善策を段階的に導入する
一度に大きなコストをかけるのではなく、まずは換気設備の調整や作業時間の見直しなど、小さな改善からスタートし、効果を見ながら段階的に進める方法が有効です。
⑤住民や顧客との対話を大切にする
においの感じ方には個人差があります。苦情が入ったときこそ、対話を通じて相手の不快感に寄り添い、迅速で誠実な対応を心がけることで、大きな信頼につながります。
におい対策は、「におわなければいい」だけでなく、「におっても納得できる関係性」を築くことが大切です。法律や数値だけに頼らず、相手の立場に立った柔軟な対応と、継続的な改善の姿勢があれば、悪臭対策は“コスト”ではなく“価値”に変わります。
よくある質問

悪臭防止法でいう4大悪臭とは?
悪臭防止法では、悪臭の代表的なにおいとして「アンモニア」「硫化水素」「メチルメルカプタン」「トリメチルアミン」の4種が特に重要視されています。これらは腐敗や排泄物、魚介類などのにおいの主成分であり、生活環境に強い不快感を与えることが多いため、規制の中心になっています。
悪臭防止法の第10条は?
第10条では、都道府県や市町村が必要に応じて、規制地域を指定し、悪臭の発生を抑える措置を講じることができると定められています。これは地域の実情に応じた対応を可能にするもので、苦情件数や環境悪化の傾向を踏まえて、柔軟に地域単位で規制を設けるための法的根拠となっています。
悪臭6物質とは?
「悪臭6物質」とは、特定悪臭物質22種の中でも、特に頻繁に問題となる6種類を指す場合があります。たとえば、アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、メチルメルカプタン、アセトアルデヒド、スチレンなどが該当することが多いです。これらは特ににおいが強く、幅広い業種で発生するため、重点的に監視されています。
悪臭の測定義務はありますか?
悪臭防止法では、規制地域内にある一定規模の事業所などに対し、においの測定や報告を義務づける場合があります。とくに苦情が寄せられた場合や行政からの指導が入った場合には、臭気指数や物質濃度の測定を行い、結果を報告する必要があります。定期的な自主測定を行うことで、トラブル予防にもつながります。
悪臭は罪になる?
悪臭自体が刑事罰の対象となることは通常ありませんが、悪臭防止法に基づく命令に従わない場合、事業者には勧告・命令・過料(行政罰)が科されることがあります。また、継続的なにおい被害が民事上の損害賠償請求につながることもあるため、軽視は禁物です。悪臭は“環境の権利侵害”として扱われるケースも増えています。
においの問題は感覚的で見えにくいからこそ、正しい知識と早めの対応が欠かせません。悪臭防止法を理解することで、近隣との信頼を守り、快適な環境づくりにもつながります。この記事を参考に、今日からできる対策を始めてみてください。


