特定悪臭物質の規制に対応するために押さえておきたい基礎知識
特定悪臭物質は、強いにおいによって生活環境に影響を与える22種類の物質です。本記事では、それぞれの特徴、発生源、規制基準、測定方法、対応の流れをわかりやすく解説します。現場で活用できる知識が得られます。
特定悪臭物質とは
特定悪臭物質とは、悪臭防止法に基づいて環境省が定めた22種類の化学物質のことです。これらは、生活環境に悪影響を与える強いにおいを持つため、事業場などからの排出が規制されています。においの問題は「感じ方」に個人差があるため、客観的に評価・測定するためには、化学的な裏付けが必要です。そこで、科学的に分析可能で、特に苦情が多く、健康や生活への影響が大きい物質が「特定悪臭物質」として選ばれました。

「悪臭物質」との違いとは?
悪臭物質という言葉は広く使われており、日常的に不快と感じるにおいの原因となる成分全般を指します。一方、特定悪臭物質は、その中でもとくに強いにおいや苦情の発生件数が多く、分析・管理が可能なものとして国が選定したものです。たとえば、し尿やごみ処理の現場でよく発生するアンモニアや硫化水素は、その代表格です。悪臭物質=すべてのくさい成分、特定悪臭物質=規制対象となる22種、と区別しておくと理解しやすくなります。
特定悪臭物質一覧
| 物質名 | においの特徴 | 主な発生源 |
|---|---|---|
| アンモニア | ツンとした刺激臭、し尿臭 | し尿処理場、畜産施設 |
| メチルアミン | 腐敗した魚のようなにおい | 化学工場、食品加工 |
| ジメチルアミン | アンモニア様、強い魚臭 | 肥料工場、皮革工場 |
| トリメチルアミン | アンモニア様、強い魚臭 | 肥料工場、皮革工場 |
| 硫化水素 | 腐った卵のにおい | 下水、温泉、し尿処理場 |
| メチルメルカプタン | 腐ったキャベツや玉ねぎ臭 | ゴム製造、化学工場 |
| ジメチルメルカプタン | 腐敗臭、腐った野菜のにおい | 排水処理、し尿処理施設 |
| 二硫化メチル | 腐敗したような強いにおい | 動植物残渣、し尿処理 |
| 二硫化エチル | 焦げたゴムのようなにおい | 化学工場、下水処理 |
| アセトアルデヒド | 果物の腐敗臭、刺激臭 | 塗料、接着剤、排ガス |
| プロピオンアルデヒド | 甘酸っぱいにおい、刺激臭 | 有機溶剤工場、接着剤製造 |
| ノルマルブチルアルデヒド | 刺激的なにおい | 化学品製造 |
| イソブチルアルデヒド | フルーツ様のにおい | 合成香料、接着剤 |
| ノルマルバレルアルデヒド | 脂肪のようなにおい | 化学合成 |
| イソバレルアルデヒド | 発酵臭、果実臭 | 香料製造 |
| 酢酸 | 酢のにおい、酸っぱい刺激臭 | 食品工場、酢製造 |
| プロピオン酸 | 酸味の強い刺激臭 | 発酵食品工場、飼料製造 |
| ノルマル酪酸 | 汗臭、腐ったバターのようなにおい | 畜産施設、堆肥場 |
| イソ吉草酸 | 足のにおい、強い体臭 | 発酵施設、し尿処理 |
| トルエン | シンナーのような甘いにおい | 塗装、印刷、化学工場 |
| キシレン | 甘い芳香臭 | 塗料、接着剤、化学工場 |
なぜ22物質が特定されているのか
選ばれた22物質は、長年の住民からの苦情データや、自治体によるにおいの測定結果に基づいて決められています。たとえば、工場周辺で問題となりやすいトリメチルアミンや、化学系事業場で使用されるトルエンなど、においの発生頻度と強さ、測定のしやすさが考慮されています。また、すべてが常に同じようににおうわけではなく、気温や湿度によっても感じ方は変わるため、こうした条件下でも安定して検出できることも重要な選定基準となりました。
法律での位置づけ(悪臭防止法の概要)
特定悪臭物質は、「悪臭防止法」という法律に基づいて規制されています。この法律は1971年に制定され、においによる生活環境の悪化を防ぐことを目的としています。工場や事業場が排出するにおいの強さや濃度を、敷地の境界線で測定し、基準を超えれば改善命令が出されるしくみです。環境省は定期的にガイドラインや測定マニュアルを更新し、自治体や企業が正しく対応できるようにしています。法の力を借りて、地域の住環境を守るしくみといえるでしょう。
悪臭に関する研究および悪臭防止技術の開発の進展、悪臭の防止に対する国民の世論の高まりを背景に1971年に悪臭防止法が制定され、特定悪臭物質の濃度による規制が始まった。
▶︎出典:悪臭防止法|フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
特定悪臭物質一覧と特徴
特定悪臭物質は、悪臭防止法により定められた22種類の化学物質です。これらは、においの強さや苦情の多さ、分析のしやすさなどを基準に選ばれています。日常生活や産業活動のなかで発生しやすく、人によって感じ方が異なるため、それぞれの特徴を正しく理解することが重要です。

覚えやすい語呂合わせや分類法
22物質を丸暗記するのはむずかしいため、語呂合わせやグループ分けが効果的です。たとえば、においの系統別に分けると次のようになります。
- アンモニア系:アンモニア、トリメチルアミン(魚の腐敗臭)
- 硫黄系:硫化水素、メチルメルカプタン(二日酔いの口臭に似たにおい)
- 脂肪酸系:酢酸、プロピオン酸、酪酸(汗や足のにおい)
- 有機溶剤系:トルエン、キシレン、スチレン(塗料やシンナー臭)
暗記に役立つ例として、「アントリ硫メチ脂トルキス(アントリ=アンモニアとトリメチルアミン、硫メチ=硫化水素とメチルメルカプタン、脂=脂肪酸、トルキス=トルエン・キシレン・スチレン)」などの略語を作るのも一つの方法です。
臭いの種類と感じ方の違い
同じ物質でも、においの感じ方には個人差があります。たとえば、硫化水素は「腐った卵のにおい」と表現されますが、濃度が低いと気づかれにくく、逆に高濃度では嗅覚がまひしてしまいます。
| 系統 | 代表物質 | においの表現例 |
|---|---|---|
| 窒素系 | アンモニア、トリメチルアミン | 尿・腐敗した魚 |
| 硫黄系 | 硫化水素、二硫化メチル | 腐った卵・ガス |
| 酸系 | 酢酸、酪酸、プロピオン酸 | 汗、すえたにおい |
| 有機溶剤系 | トルエン、スチレン | ペンキ、接着剤のにおい |
とくに、トリメチルアミンやメチルメルカプタンは極めて低濃度でも強く感じられるため、検出しやすく、苦情につながりやすいにおい物質です。
化学式と性質の簡単な解説
化学式は苦手という方も多いですが、基本だけおさえておくと、においの性質を理解する手がかりになります。
- アンモニア(NH₃):水に溶けやすく、アルカリ性。し尿処理施設で発生しやすい。
- 硫化水素(H₂S):極めて毒性が高く、下水処理や火山地域で発生。濃度が高いと命にかかわる。
- トリメチルアミン((CH₃)₃N):強烈な魚臭。低濃度でも嗅覚に強く刺激を与える。
- トルエン(C₆H₅CH₃):ベンゼン環をもつ芳香族炭化水素。溶剤や印刷業で多用される。
化学式の理解が深まれば、どの施設でどの物質が発生しやすいかもイメージしやすくなります。とくににおいと化学構造は密接に関連しており、現場での対応にも役立ちます。
主な発生源とその背景
特定悪臭物質は、私たちの身のまわりにあるさまざまな施設や活動から発生します。発生源は大きく「生活系」と「産業系」に分けられ、それぞれに特徴的な物質が関係しています。また、複数の物質が同時に放出される場合もあり、においの強さや性質が複雑になることもあります。この章では、どのような場所でどんな悪臭物質が生まれるのかを具体的に見ていきます。

畜産、し尿、汚水処理など生活系の発生源
生活系の発生源では、畜産業や下水処理施設、し尿処理場などが代表例です。たとえば、豚舎ではアンモニア(NH₃)や硫化水素(H₂S)が高濃度で検出されることがあり、夏場の高温多湿時にはにおいが強まりやすくなります。
また、し尿処理施設では、微生物による分解過程でトリメチルアミンやメチルメルカプタンが発生しやすく、近隣住民からの苦情につながるケースもあります。こうした施設では、通気や脱臭装置の整備が不可欠です。
農村部や都市郊外では、堆肥づくりの工程でも酪酸などの短鎖脂肪酸がにおいの原因になります。これらは天然由来である一方で、におい自体は強烈なため、近隣との共存を考慮した対策が求められます。
塗装、化学、印刷など産業系の発生源
産業系では、工場や製造現場で使用される有機溶剤や化学原料が悪臭物質の発生源となります。塗装工場ではトルエンやキシレン、スチレンなどが使われ、乾燥時に揮発して空気中に放出されます。
印刷工場では、インクの溶剤として使用される化学物質がにおいのもとになります。とくに密閉空間での作業が多い場所では、適切な換気や排気が求められます。
また、化学系の製造業では、原材料の反応や廃液の処理過程でさまざまな悪臭物質が生まれます。設備の老朽化や作業ミスが原因でにおいが外部に漏れる事故もあり、定期的な保守点検が欠かせません。
複数物質が混在するケースと注意点
悪臭問題の多くは、単一の物質だけでなく、複数の悪臭物質が同時に存在する「複合臭」が原因となっています。たとえば、し尿処理場ではアンモニア・トリメチルアミン・硫化水素が同時に発生し、それぞれのにおいが混じり合うことで、より強烈で不快なにおいになります。
このような場合、原因物質を特定するのが難しく、測定や対策が複雑になります。特に、嗅覚では感じにくい物質でも他のにおいと混ざることで存在感が増すことがあり、専門的な分析機器や臭気判定士の判断が重要です。
複合臭への対応では、脱臭装置の多段階処理や現場ごとの濃度測定が有効です。1種類の対策では限界があるため、総合的な管理体制の構築が求められています。
規制基準と測定方法のしくみ
特定悪臭物質の発生を抑えるには、においの強さや濃度を「測り」、一定の基準に基づいて「規制」する必要があります。悪臭防止法では、においの発生状況に応じて3つの規制方法を定めています。また、それぞれの現場で正確な測定を行うために、専門的な機器や資格者の存在が重要です。この章では、規制のしくみと実際の測定方法について解説します。

濃度規制の仕組み(1号・2号・3号の違い)
悪臭防止法では、においの排出状況に応じて次の3つの規制方法が設けられています。
- 第1号規制:敷地境界における空気中の濃度規制。一般住民の生活環境を守るため、敷地外でのにおいを制限します。
- 第2号規制:排出口における排出濃度・流量の規制。工場などの設備から出るにおいの強さを直接管理します。
- 第3号規制:排水中の悪臭物質の濃度規制。水処理施設や食品工場など、水を通じてにおいが広がるケースに対応します。
これらの規制は、自治体が地域の状況に応じて選択し、基準値を定める仕組みです。たとえば、住宅密集地では第1号規制が重点的に採用されることが多くなります。
測定マニュアルの概要(誰がどう測る?)
においの測定には、環境省が発行している「悪臭防止法に基づく測定マニュアル」が用いられます。このマニュアルには、サンプリングの手順、必要な測定機器、分析方法などが細かく記されています。
測定は、自治体の職員や委託された環境測定機関が行います。事前に現場の状況を確認し、風向きや気温なども記録します。採取された空気は専用のバッグに封入され、分析機関で化学的な成分測定が行われます。正確なデータを得るためには、手順通りの作業が必須であり、測定者の熟練度も結果に大きく影響します。
ガス検知・分析機器の紹介とにおいの単位
悪臭物質の測定には、化学分析機器が活躍します。代表的な機器には以下のようなものがあります。
- ガスクロマトグラフ(GC):混合されたガスを分離して分析
- イオンクロマトグラフ(IC):酸性・塩基性の物質を分離して測定
- 光学式ガス検知器:現場でリアルタイムにガス濃度を測定可能
測定値は通常、「ppm(parts per million)」や「ppb(parts per billion)」で表示されます。たとえば、アンモニアの規制基準は地域によって異なりますが、敷地境界では0.1ppm以下に設定されているケースが多いです。これらの単位は、目に見えないにおいを「数値化」するために欠かせません。
嗅覚測定と臭気判定士の役割
化学的な測定だけでなく、人の「においの感じ方」も重要な評価基準です。そこで活躍するのが、国家資格である臭気判定士です。彼らは、嗅覚によって「臭気指数」という指標を測定します。
たとえば、試料を何倍に薄めたらにおいを感じなくなるかを調べ、数値として表す方法(希釈法)が使われます。この数値が高いほどにおいが強いと判断されます。
臭気判定士は、複雑なにおい環境の中でも原因物質を特定したり、数値化しにくい複合臭の強さを判定したりと、化学分析だけではカバーできない分野を補っています。
においは目に見えず、感じ方も人それぞれですが、こうした規制と測定技術によって、環境と生活を守ることができるのです。
実際の取り組みとトラブル事例
特定悪臭物質に対する規制が整っていても、現場では住民からの苦情や想定外のにおい問題が日常的に発生します。その背景には、季節変動や設備の老朽化、作業手順のわずかな違いなどがあり、対応には迅速かつ柔軟な判断が求められます。この章では、におい苦情が発生したときの調査フローから、企業・自治体の具体的な取り組みまでを紹介します。

苦情からの調査と対応フロー
においに関する苦情は、自治体の環境課や生活環境部門に電話やWebで寄せられることが多くあります。通報を受けた職員は、以下のような手順で対応します。
- ①現地調査の実施:通報者宅周辺や発生源と疑われる施設を確認
- ②嗅覚や機器による初期測定:臭気判定士による評価や簡易ガス検知器の使用
- ③関係事業者への聞き取り:作業状況や排気設備の状態を確認
- ④必要に応じた改善指導や報告書作成
夏場など気温が高い時期には、し尿処理施設や汚水処理場の周辺で腐敗臭に関する苦情が増えることがあります。原因としては、送風設備の不具合や処理工程の一時的な負荷増大などが挙げられ、調査により改善措置や設備の見直しが必要とされるケースも少なくありません。
測定と報告の実務プロセス
苦情を受けての調査では、科学的な裏付けが求められるため、専用機器による正確な測定と報告書の作成が不可欠です。
- 採取方法:活性炭吸着やテドラーバッグによる空気採取
- 分析機関へ送付:ガスクロマトグラフ等による定量分析
- 測定結果の記録:濃度、臭気指数、現場状況などを時系列で記載
- 改善提案:結果に基づいた施設側への改善提言を含める
測定データは、自治体が住民に説明する際の信頼性にも関わります。事業者も、自社の管理状況を把握し、再発防止策を立てる材料となります。
自治体・企業の工夫と改善例
におい問題は、規制だけでなく「普段からの配慮」が大きな鍵を握ります。たとえば、ある食品加工工場では、臭気の強い工程を夜間から昼間に変更。これにより、苦情件数が半分以下に減少しました。
また、自治体側でも、以下のような取り組みが進んでいます。
- 臭気センサーによる常時モニタリング
- 住民との連携会議の開催
- 改善報告書の公開と地域説明会
においは見えないからこそ、誠実で透明な対応が信頼につながります。測定値や対応状況を共有することが、苦情の抑制と地域との共存につながるのです。
知っておきたいトピック集
特定悪臭物質の管理には、測定方法や規制基準の理解に加えて、現場で活かせる実践的な知識も欠かせません。この章では、資格試験や講習で役立つ覚え方の工夫、最新の脱臭技術、そして現場でよくある誤解とその正しい知識について紹介します。現場対応力や応用力を高めるための「知っておきたい」視点をまとめました。

測定のコツや覚え方(試験・講習向け)
臭気判定士などの試験では、特定悪臭物質22種の名称・化学式・発生源などの暗記が求められます。単純な暗記では忘れやすいため、分類や語呂合わせを活用すると効果的です。
【例】アントリ硫メチ脂トルキス
アンモニア・トリメチルアミン・硫化水素・メチルメルカプタン・脂肪酸系・トルエン・キシレン・スチレンの略。
また、測定の実技では「気温や風向き」「採取時間帯」「現場の作業状況」など、環境要因の記録が評価されます。
測定時のポイント
- サンプリングは鼻より少し高い位置が基本
- ガス検知器はゼロ校正を忘れずに
- 分析機関との事前打ち合わせでミスを防ぐ
これらのコツは、試験だけでなく実務でも大いに役立ちます。
においを減らす技術や製品の最新動向
悪臭対策の技術は年々進化しており、現場の規模や特性に応じた製品が登場しています。近年注目されているのは以下のような方法です。
- オゾン発生器:酸化分解により有機臭を除去。小型でも効果が高い。
- バイオフィルター:微生物の力で分解。し尿や汚水処理場に導入例多数。
- 活性炭吸着塔:揮発性のにおいを吸着。印刷・化学工場で広く使用。
また、スマート臭気モニタリングやIoT連携型センサーによるリアルタイム監視も広がりを見せています。これにより、においの傾向をデータ化し、対策の最適化が可能になります。
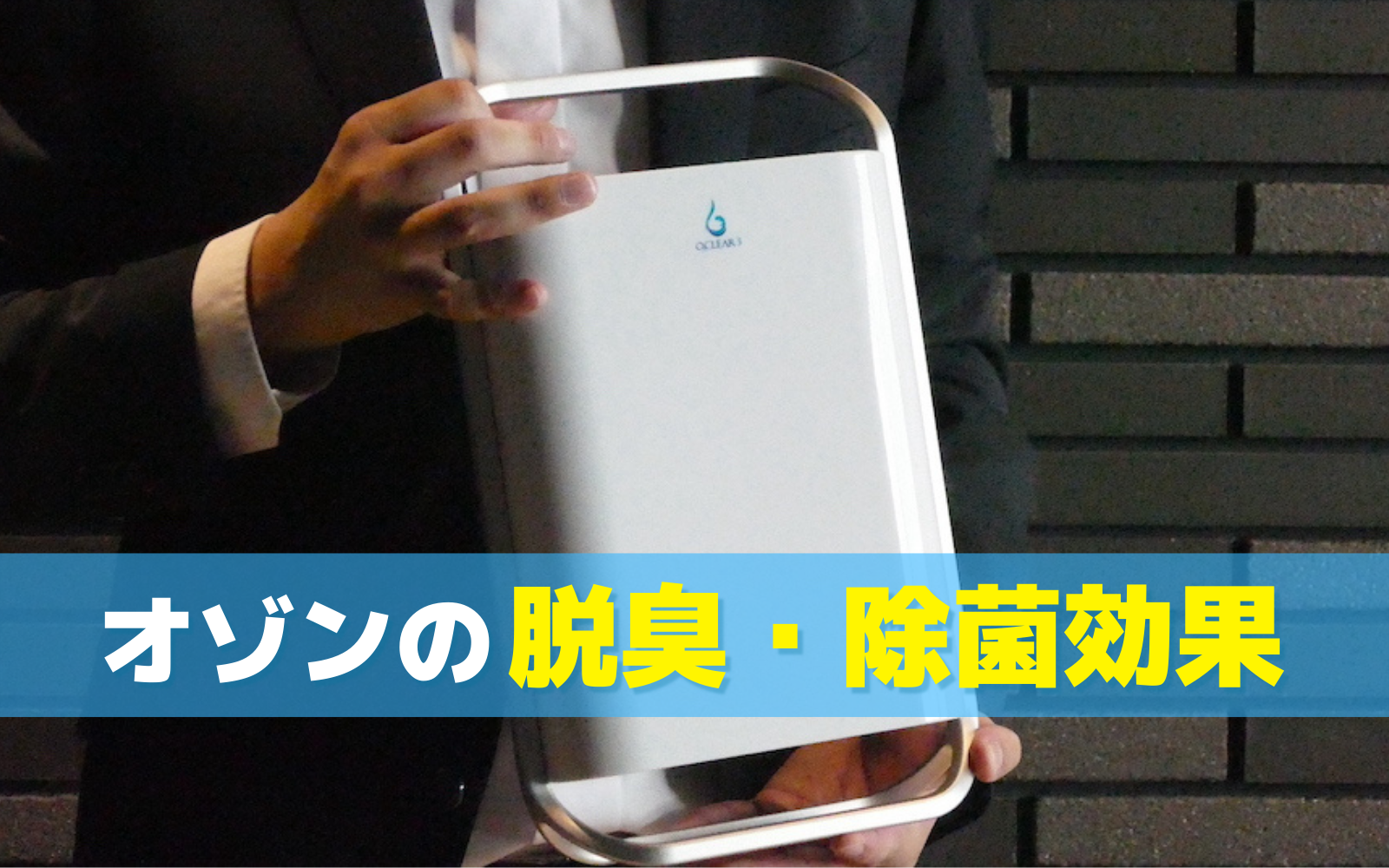
ニオイ対策をする上で、空気清浄機や芳香剤といった他の選択肢と比べた、オゾン発生器が持つ優れたところを、オゾンの化学的な性質からご説明します。
▶︎ 記事を読むよくある誤解とその正しい理解
においの管理においては、現場や住民の間に誤解が生じることがあります。誤解はトラブルの種になるため、正確な情報共有が不可欠です。
| よくある誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 臭いがなければ問題ない | 一部の悪臭物質は嗅覚で感知できない濃度でも健康影響がある |
| においの強さは数値で完全に表せる | 数値と感じ方は一致しないことが多く、嗅覚評価も重要 |
| 一度対策すれば再発しない | 設備の劣化や運転条件の変化で再び問題が起こることもある |
こうした認識のズレをなくすためには、職員・事業者・住民が共通の知識を持つことが大切です。説明会や資料提供を通じた「におい教育」も今後ますます重要になります。
正確な知識と最新の対応力を備えることが、においトラブルの予防と信頼構築への第一歩です。最後に、特定悪臭物質に関して多くの人が気にしている疑問を「よくある質問」として整理します。
よくある質問

4大悪臭物質とは何ですか?
4大悪臭物質とは、「アンモニア」「硫化水素」「トリメチルアミン」「メチルメルカプタン」の4つを指します。これらは特定悪臭物質22種の中でも、においの強さや苦情の多さが際立っており、環境測定でも頻繁に対象となる物質です。いずれも極めて低濃度で人がにおいを感じやすく、し尿処理場や畜産施設などでよく発生します。
3大悪臭とは何ですか?
3大悪臭とは、「アンモニア」「硫化水素」「トリメチルアミン」の3つを指すことが多いです。特に生活環境において発生頻度が高く、強烈で不快なにおいとして知られています。たとえば、アンモニアはし尿や生ごみに、硫化水素は腐敗や下水に、トリメチルアミンは魚の腐敗臭に由来します。これらは早期対応が求められる代表的な悪臭物質です。
臭い物質のランキングは?
臭い物質のランキングは、においの強さ(しきい値)や不快度に基づいて決められることがあります。一般的に不快度が高いのは、1位:トリメチルアミン(腐った魚のにおい)、2位:メチルメルカプタン(腐った玉ねぎ)、3位:硫化水素(腐った卵)などです。これらは非常に低濃度でも強くにおい、苦情が出やすい代表格です。
特定悪臭物質のリストは?
特定悪臭物質のリストは全部で22種類あり、悪臭防止法で定められています。代表的なものとして、アンモニア、硫化水素、トルエン、スチレン、酢酸、酪酸、トリメチルアミン、メチルメルカプタンなどが含まれます。これらは環境省の公式資料に一覧で掲載されており、においの強さや発生源によって分類されます。
五大悪臭とは何ですか?
五大悪臭とは、悪臭の代表的な系統である「アンモニア臭」「硫化水素臭」「有機酸臭(酢酸など)」「アルデヒド臭(アセトアルデヒドなど)」「芳香族炭化水素臭(トルエンなど)」を総称した呼び方です。明確な定義はありませんが、さまざまな業種で共通して発生しやすく、対策が重視されている臭気のカテゴリーとして扱われています。
特定悪臭物質に関する正確な知識を持つことは、においによる苦情対応や施設運営、地域との良好な関係づくりに直結します。法制度や測定技術を理解し、現場ごとの課題に的確に対応できる力を身につけて、快適で持続可能な生活環境の実現に役立ててください。




